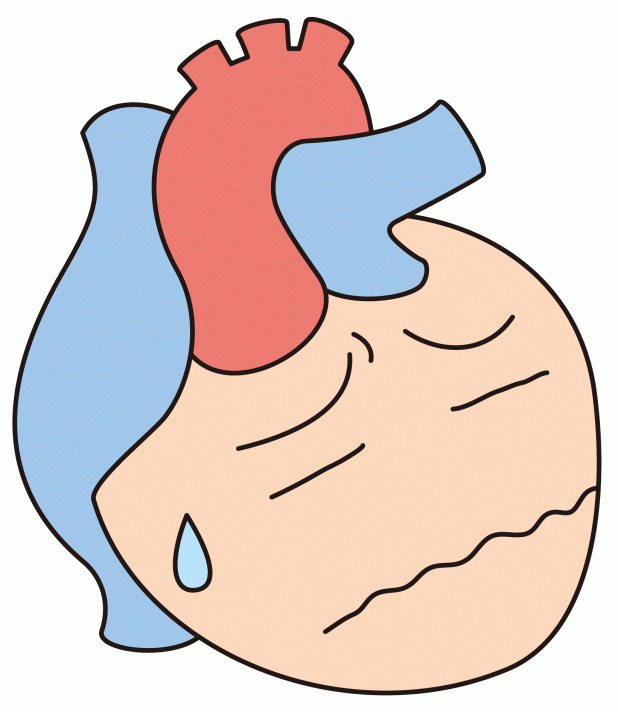循環器内科 池田祐樹
心不全とは、心臓の障害が原因となって起こる体の不健全な状態のことを言います。
心臓のポンプ機能
人間が生きていくには、体の各臓器が働くのに必要な酸素と栄養が行き渡ることが必要です。その酸素と栄養は血液に乗せて運ばれ、この血液を循環させるためのポンプ機能を持っているのが心臓です。心臓のポンプとしての機能はポンプの駆出力を生み出す心筋と、血液の流れの方向性を決める一方向弁により構成されます。心 (室)筋からなる袋状の右心室と左心室、これらの入口と出口にある4つの弁 (大動脈弁、僧帽弁、肺動脈弁、三尖弁)が心臓を構成します。心筋が伸び袋状の心室が膨らむことで血液が流入し、心筋が縮み心室が小さくなることで血液が流出します。右心系には全身から血液が流入、肺へと流出し、左心系には肺から血液が流入、全身へと流出するのが、正常な循環の流れです。
心臓のポンプ機能の結果、起こる現象は次の2つで説明できます。流入障害つまり血液のうっ滞と、流出障害つまり低拍出による症状で、これらのどちらかまたは両方がある状態を心不全と言います。
心不全の症状
心不全の症状は、うっ滞と低拍出の2種類に分類されます。うっ滞症状としては、手足や顔のむくみ (浮腫)、肺のむくみ (肺水腫)、肝臓の腫大、腹水などが挙げられます。一方、低拍出の症状は多彩で、意識がぼーっとしたり、強い倦怠感が見られたり、腹部の不快感が見られたりします。
心不全の原因
心不全を起こす心疾患には様々のものが存在します。大きくは、①心臓のポンプ機能 (収縮機能、拡張機能)の低下、②弁膜症、③不整脈、④先天性心疾患、その他心臓以外の原因によって心不全の症状を引き起こす疾患 (貧血、甲状腺機能異常など)があります。①を起こす疾患では虚血性心疾患 (狭心症、心筋梗塞)、心筋症 (拡張型心筋症、肥大型心筋症、アミロイドーシス、薬物毒性など)が代表的です。
心不全の原因疾患の診断には、病歴や家族歴の問診、身体所見の診察に加えて、様々な検査を組み合わせて総合的に診断します。ただし、一人の患者さんに存在する心不全の原因が一つだけでなく二つまたは三つ以上存在する場合もあります。
心不全の治療
心不全の治療は大きく、①原因心疾患に対する治療と、②心不全という不健全な状態を改善する治療に分けられます。①には虚血性心疾患や不整脈に対するカテーテル治療や薬物治療、弁膜症や先天性心疾患に対する手術、治療法の存在する心筋症に対する治療などが挙げられます。②には利尿剤、血管拡張薬、強心薬、心筋保護薬などの薬物治療が中心となります。また、貧血や甲状腺機能異常などの心臓以外の原因が存在する場合にはそれに対する治療も並行して行います。薬物治療でも病状が悪化し、適応のある患者さんに対しては、人工心臓や心移植などが選択される場合もあります。
近年、まだ心不全ではないが、将来心不全を起こしやすい人 (高血圧や糖尿病の患者さん)を早期から見極め、心不全へと進展させない=予防が重要であることが重要であると言われています。そのためには、このような患者さんに対する生活習慣の指導、心不全の初期症状に早く気づくこと、などの重要性が認識されています。
さいごに
心不全の症状は気づかれにくく、加齢やただ疲れているだけなどといった判断で見過ごされることも少なくありません。上記の症状に当てはまる場合は、一度専門医へ相談することが重要です。